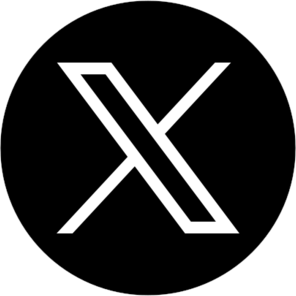【発表者編】グループディスカッション、どんな表情をしたらよい?どんな表情、気にすべき?
こんにちは。カチメン表情監修の清水建二です。
本日のコラムは、グループディスカッションにおいて気をつけたい表情【発表者編】です。
一般的な就職活動の書籍等では、役割別の評価ポイント、言葉使いや発声の仕方、論理性、内容等に焦点が当てられます。
本コラムでは、そうした書籍ではほぼ触れられないものの、ディスカッション中のコミュニケーションに大きな影響を及ぼす、表情の読み方について解説します。
面接時だけでなく、社会人になった後も役立つポイントです。
グループディスカッションにおける主な役割は、司会、発表者、タイムキーパー、書記の4つです。
司会編とタイムキーパー・書記編は、以下のリンクからお読みください。
司会編はこちら タイムキーパー・書記編はこちら
| 発表者の役割 |
発表者は、グループで導き出した結論とその過程を、指定された時間内で論理的にわかりやすく伝える役割。
要点を整理し、相手に納得感を与える説明力が求められます。
司会、発表者、タイムキーパー、書記の中で、発表者は、表情を読む能力も作る能力も共に必要とされ、忙しい役割だと思います。
議論でまとめた意見をどう表現し、強弱をつけて伝え、同時に聞いている他のメンバーが理解しているか、理解できるように発表しているかに気を配るようにします。
| 発表内容を理解していない人、見抜けますか? |

最初に表情を読む能力についてです。実際のケースを通じて確認しましょう。
問題:
次のシーンは、実際のディスカッション中の一コマです。
あなたはグループを代表してグループの意見を発表しています。
あなたと異なるグループのメンバー①~④が発表を聞いています。
①~④のどのメンバーにどんな声をかけますか?

解説:
発表者が優先的に気づけるようにしたいのは、他のメンバーが発表者の発表を理解しているか否かです。
発表の内容を理解することは、有益な議論の前提となるからです。
理解なくして、議論は成立しません。
どのメンバーが理解していない表情をしているか。正解は②。
②のメンバーは、眉が中央に寄り引き下げられる表情をしています。
この動きがあると、眉間にしわが寄ります。この表情は、私たちが熟考しているときに動きます。
早口で聞き取れない。あるいは、熟考するほど発表の内容が難しくなっている。
はたまた、内容は理解しているものの、自身の意見とすり合わせ、何かを言おうとしている瞬間かも知れません。
いずれにせよ、同じペースで発表をし続けない、ということが大切です。
発表のスピードを緩めたり、言葉を変えて説明しなおしたり、②のメンバーに質問を促したりするとよいでしょう。
| 発表時、どのような表情を意識するべきか |
次に表情を作る能力についてです。
自身の気持ちを表情に乗せる方法については、これまでのコラムで様々にお伝えしてきました。
熱意・真剣度の伝え方、興味関心の伝え方、笑顔の伝え方、面接で表情が重要な理由、表情のクセあれこれ等々です。
まだお読みになっていない方は、是非読んでみて下さい。
ここで一つ考えて頂きたいことがあります。
自分自身の意見を発表するときとグループの総意を発表するときの大きな違いは何だと思いますか?
グループの総意を発表するのですから、グループで導き出した結論とその過程で皆が力点をおいている箇所を意識しながら、発表をすることが重要です。
発表者自身の感情よりもグループの感情を優先させなくてはなりません。
ここを取り違えることなく、皆の意見が印象的に伝わるよう表情作りを工夫しましょう。
この視点は当たり前のようで、意外に見落としている方がいるのも事実です。
会社の業務は、多くの場合、チームで行います。
チームで一丸となり、気持ちを一つにし、業務を遂行します。
チームのメンバーの気持ちを無視してスタンドプレーをしていてはダメなのです。
発表者に限りませんが、就職面接や説明会においてグループディスカッションやチームで何かをさせる目的は、チームプレイが出来るか否かも評価しているのです。
グループディスカッションにおいて発表者は目立つため、ポジティブに評価されやすいと思われがちですが、スタンドプレーに走れば、ネガティブにも評価されやすいのです。
発表者になった方は、ポジティブな側面が光るよう、表情の読み方・作り方を工夫しましょう。
次回は、タイムキーパーと書記のコミュニケーション方法についてお話します。
ではでは、実践を重ねて下さい。
※記事中の画像の権利は、株式会社空気を読むを科学する研究所に帰属します。無断転載を禁じます。