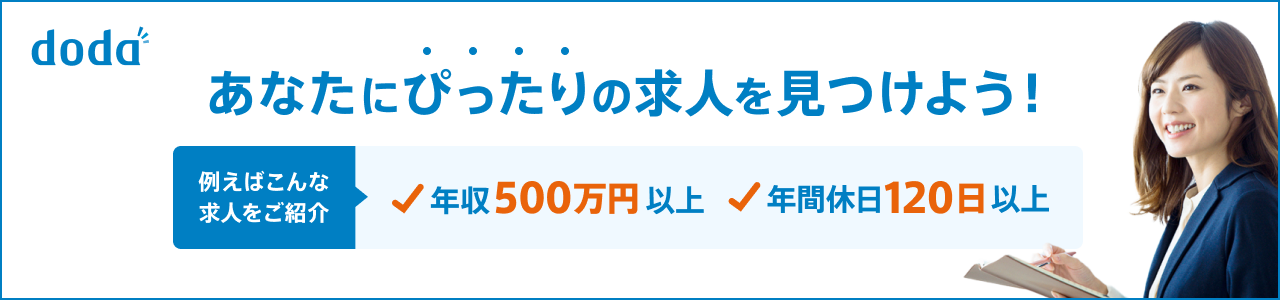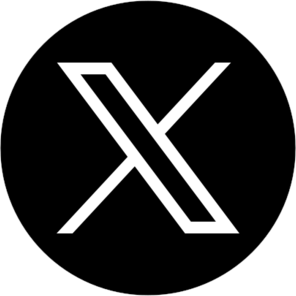・応募者が希望する職種ではどのような要素、経験、性格が問われるか
・採用側が配属しようと考えている職場の仕事内容、人間関係での適用性がありそうかどうか
というものがあります。
日本の就職活動では職種別採用を除き、面接時に配属先が明確に決まっていないことも多いです。
そのため、あくまでも自身が希望する仕事の内容で問われるものを考えた上で企業側にアピールできることを練っていきましょう。
比較的小規模の企業の場合、新卒でも職種別採用をしていることがありますので、職種に興味が強い方は応募を検討してくださいね。

配点が高くなくても時々聞かれる質問
私自身が就活生だった頃、そして、現在、就職指導をしていて「これを聞いて何が知りたいのかな」と思う質問があります。
その代表格が短所についての質問です。
前回のコラムのお買い物に当てはめてみてください。
テレビを買うとき、商品の短所を知りたいでしょうか?短所はどのテレビを買うかの候補が絞り込めないときに見ていく部分ではないでしょうか。
面接では長所や力を入れて取り組んだ話であれば、具体的にいい部分が際立つ伝え方をするほどに面接官を「なるほど!」、「うんうん!」と頷かせることができます。
そのため、話を具体的にする、広げるなどすればいい評価を獲得できます。
一方で短所はどうでしょうか。
広げていくほどに悪い話が際立ちますね。
そのため、嘘をつかないまでもできる限り悪く言わないように小さくまとめると思います。
それを知って参考になるものは実はありません。
就職指導の授業で「なぜ短所を聞いてくると思いますか?」と生徒に質問すると、
「短所をどう克服したのかを知りたいから」
「自分の短所に気づいているかどうかを知りたいから」
のいずれかの回答が大半です。
しかし、正解は「聞く意味は特にない」です。
・長所を聞いたから短所も聞いておこう
・自分自身聞かれたから聞いておこう
論理的に考えるとこの2つのことが導き出せます。
ちなみに、採用担当になぜ短所を聞くのかと聞いても生徒と同じ回答をします。
あとは、「短所を素直に言う人は仕事をする上で好ましくないから」と頑張り出すように話します。
しかし、基本的には短所が出たときに注意すれば済む話です。
採用判断に影響を与えるものではありませんね。
こうした意味がないあるいはさほどない質問は多く存在します。
どれにも意味がありそうと考えてしまい、知らないうちに囚われてしまっていることが多いので、コラムを通じて、自分で考える力をしっかりと身に付けてくださいね。
面接官が聞いてくるから意味があるという感覚は思考停止です。
常識をまずは疑って、意味を考えられるようにしていきましょう。
そうすれば、自動的に回答にどんな要素を盛り込むべきかも理解できます。