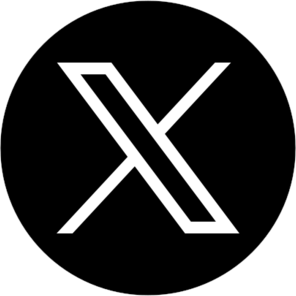インターン選考は数で勝負! 限界突破でチャンスを掴もう
こんにちは、トイアンナです。
インターンシップの季節が近づき、「何社くらい応募すればいいの?」と悩んでいる皆さんも多いのではないでしょうか。
そこで、今日は結論から。
インターンシップは、思い切って多数エントリーした方が勝ちです。
| 「多すぎる」なんてことはない! 企業は辞退を織り込んでいる |
まずは、企業側の視点を理解しましょう。
大手企業の採用担当者は、辞退率の高さを見込んで、多めに通過連絡を出しています。
私も多数の就活イベントを支援してきましたが、リアルで開催する就活イベントって「雨が降っただけで3割も出席者が減る」のですよ。
それくらい学生は辞退しているので、あなたひとりが辞退するかどうかは、誤差、統計の範囲です。
たとえば、最終的に50人参加してほしいところ、辞退率30%を見込んで71人に説明会の案内を出しています。
辞退を気にしすぎる必要はありません。
しかし、応募しなければ後から「やっぱりエントリーすればよかった」と思っても間に合いません。
だからこそ、就活では「ありったけエントリーして、キャパを超えたら辞退する」のが最善手となるのです。
自分の「得意業界」「苦手業界」を発見できるチャンス |

次に、多くの企業へ応募することで得られる貴重な情報があります。
それは自分が「通過しやすい業界」と「通過しにくい業界」の違いです。
たとえば、あなたが業界を絞らず20社に応募したとします。
そうしたら、IT企業は3社中3社通過できたのに、コンサルは4社中1社しか通過せず、メーカーに至っては3社全落ち、という結果が出たとします。
このデータからあなたは「自分はIT企業との相性が良い」という重要な気づきを得られます。
そうすれば、秋冬インターンや本選考では業界を絞っても内定しやすくなるのです。
幅広い業界にチャレンジすることで、自分の強みが見えてくる。
また、業界に限らず選考通過した企業の特徴を分析することで、「自分はこういう企業文化と相性が良いんだ」という発見もあります。
これは自己分析よりも遥かに具体的です。
私は就活で第一志望だった「伝統的な日系メーカー」に一次選考で落とされまくりました。
一方、「キラキラした業界」では受けがよかった。
自分はキラキラなんて、していないのに、です。
だったら……と、いわゆるキラキラ企業を受け、内定を獲得しました。
自分の望みと、適正は別です。
あなたの強みを査定する場所として、夏インターンを活用してください。
|
たとえ選考を辞退してもリスクはほぼ「ゼロ」
|
インターン選考を辞退して失うものは、ほとんどありません。
仮に辞退したからといって罰金が発生するわけでもなく、法的な問題が生じるわけでもありません。
せいぜい、最悪のシナリオは「その企業の本選考を受けられないかもしれない」だけです。
しかし、そもそも辞退を決めた企業を、本選考で再チャレンジするとも考えづらい。
であれば、辞退していいのです。
そして、学生の中には「一度内定を辞退したら、その企業にはもう二度と応募できない」と思い込んでいる人もいますが、それは大きな誤解です。
企業はビジネスライクに対応しています。
特に大手企業ほど、「辞退=NG」という単純な判断はしません。
堂々と自分の意思決定をすればいいのです。
| トップ層の学生と知り合い、レベルアップできる |

インターン選考を進めていくと、特に難関企業のイベントや選考では「就活ガチ層」と出会うことになります。
この経験には、かなりの価値があります。
同年代のトップ層を知ることで、自分の立ち位置がわかり、モチベーションも上がるからです。
「あの人のように準備しないと」「この質問への答え方は自分も使わせてもらう」など、具体的な目標設定ができるからです。
| 量は質を生む! インターンへ多数エントリーしよう |
インターンシップで応募する企業の数は「多ければ多いほど良い」と言えます。
たとえキャパを超えるくらいエントリーしても、得られるメリットは大きいのです。
最後に、いますぐできる次のステップを書いておきます。
| ①まずは興味のある会社を5社エントリー ②その会社の競合他社をChatGPTに質問して追加で5社エントリー ③なんとなく目に入って気になった企業10社へエントリー ④自分が「なんとなく行きたくない」と感じている食わず嫌いの企業5社も追加でエントリー (選考を通じ、自分がなぜその業界を苦手としているのかがわかります。そして、もし誤解がとけたらその企業が第一志望になる可能性もあるのです) |
多くのインターンに応募することで、あなたは貴重な自己分析データを手に入れることができます。
そして、その情報こそが本選考での武器になります。
今からでも遅くありません。まずはエントリー社数を増やしましょう!